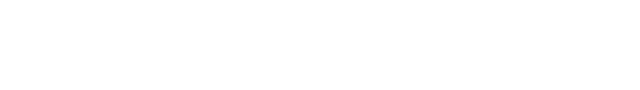免疫は「攻撃」ではなく「調和」をつくる仕組み - 京都から世界へ。坂口志文先生のノーベル賞受賞に寄せて
「先生、炎症を止める薬をください。」
診療の現場で、患者さんから最も多くいただく言葉のひとつです。
しかし、この問いにすぐに答えることはできません。炎症は、単に止めるべき“悪”ではないからです。
炎症は「止めるべきもの」ではない
炎症とは、体が自分を守り、修復を始めるための反応です。感染や外傷、手術後など、組織が傷つくとまず炎症が起こります。
これは防御反応であり、生命の正常なプロセスの一部です。
ところが、この炎症が長引きすぎると、自らの組織を傷つけてしまう。そこで重要になるのが、「炎症を終わらせる仕組み」です。
免疫の終息を担う「制御性T細胞」の発見
坂口志文先生が発見された「制御性T細胞(Treg)」は、この“炎症を終息させる”働きを担う細胞です。
免疫はこれまで「攻撃のシステム」として理解されてきましたが、坂口先生は、免疫には自らを鎮める回路があることを明らかにされました。
これは、免疫が単なる戦いの道具ではなく、体内の調和を保つ精密なシステムであることを示した画期的な発見です。
京都大学が生んだ免疫学の系譜
私は京都大学で胸部外科の研修を受け、その後、米国メイヨークリニックとミシガン大学の免疫学教室で移植免疫の研究に携わりました。
外科医として炎症を目の前で見つめ、研究者として免疫を分子レベルで学ぶ中で、「免疫とは、攻撃ではなく整える仕組みである」と実感するようになりました。
そして、この視点の原点もまた、京都大学の医学の系譜の中にあります。京都大学は、世界に誇る免疫学の源流を生み出してきました。
抗体の「多様性」を発見した利根川進先生、
免疫のブレーキ分子PD-1を見出した本庶 佑先生、
そして免疫の終息機構を明らかにした坂口志文先生。
三人はいずれも京都大学の流れを汲み、それぞれが免疫の「創造・制御・終息」を世界に示されました。
京都から、免疫学の三つの柱が世界へ発信された――。
それは偶然ではなく、生命を調和の中で理解しようとする京都の学風があったからだと思います。
炎症を整えて終わらせる医療へ
私自身も、胸部外科の現場で炎症と修復の間を見つめ、アメリカで免疫の最前線を学び、いま出雲で漢方を通じて「整える医療」を実践しています。
炎症を完全に止めるのではなく、必要な炎症を許容し、体が自らバランスを取り戻す方向へ導く。それが、現代医学と東洋医学をつなぐ医療の形だと感じています。
漢方の「陰陽の調和」は、炎症のメカニズムと深く響き合います。炎症は“陽”の反応、修復は“陰”の働き。
坂口先生の研究は、この東洋的な概念を現代免疫学の言葉で裏づけたものといえるかもしれません。炎症を止めるのではなく、整えて終わらせる。
終わりに
免疫は戦いではなく、調和の仕組み。その理解が、より安全で、より本質的な医療につながるはずです。京都大学の偉大な先生方が示された“免疫の調和”。
その思想を、私たち臨床の現場でも生かし、人の体がもつ「治る力」を信じて支える医療をこれからも実践していきたいと思います。